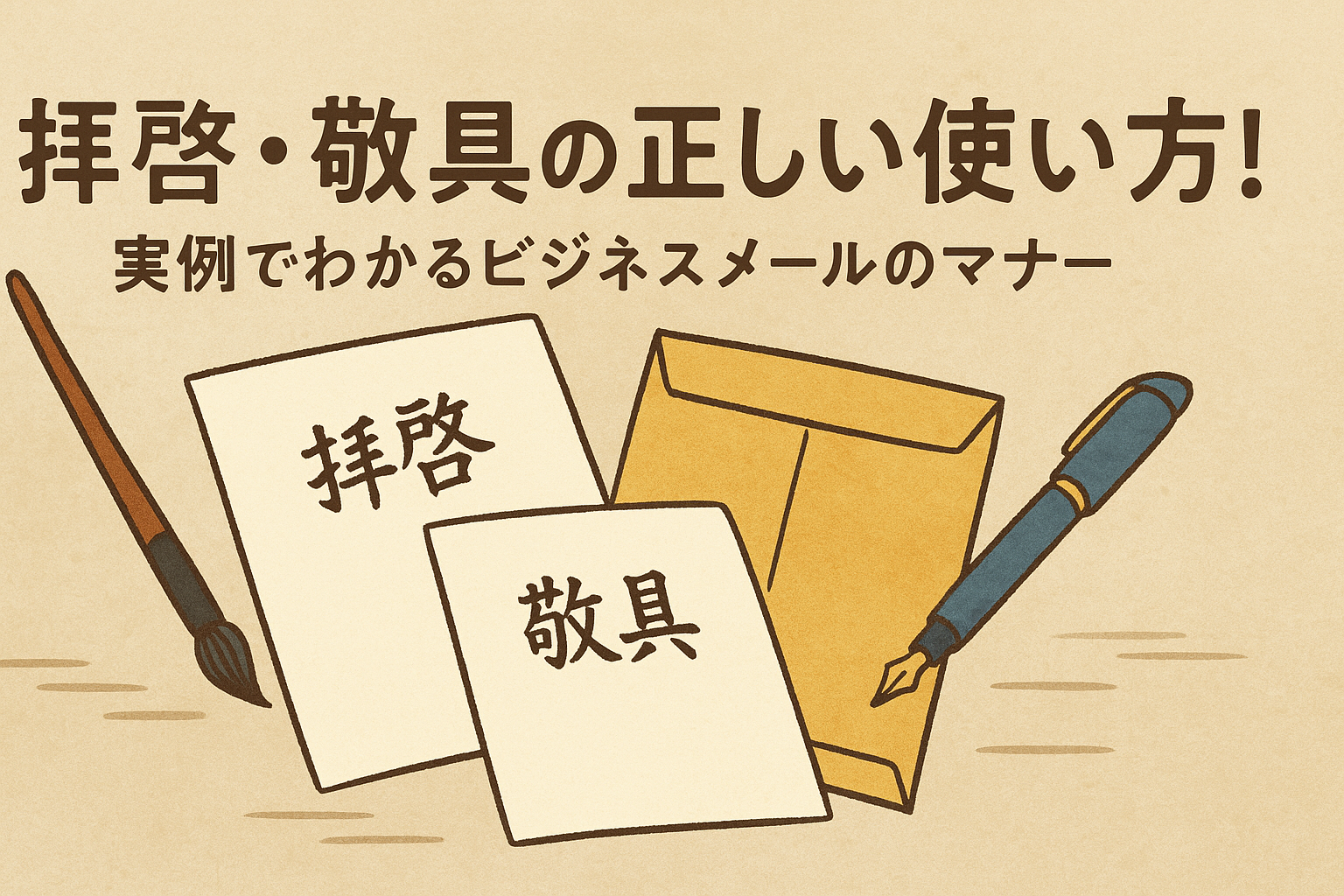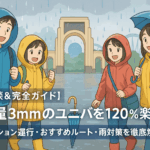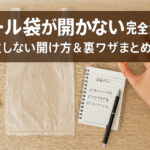「拝啓」「敬具」は、日本語のビジネスメールや手紙に欠かせないマナー表現です。
正しく使いこなすことで、相手に誠実さや信頼感を与えることができる一方、誤った使い方をすると、ビジネス上の信頼を損ねてしまうこともあります。
本記事では、「拝啓」「敬具」の意味や正しい使い方、シーン別の実例、さらには英語表現やよくある失敗例まで、徹底的に解説します。
これから社会人になる方はもちろん、すでに仕事で手紙やメールを書く機会の多い方にも必見の内容です。
拝啓・敬具の基本理解
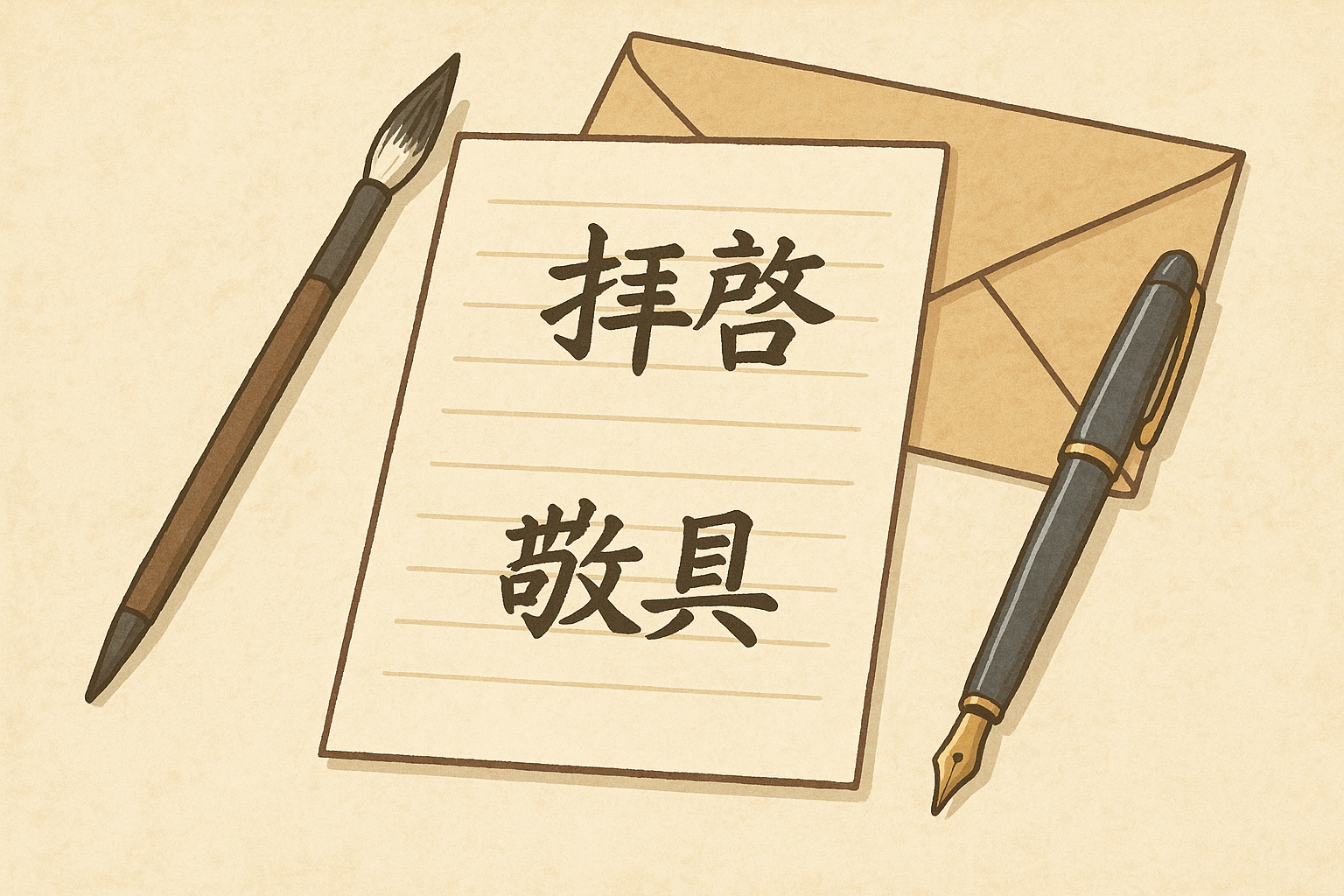
拝啓と敬具の意味とは?
「拝啓(はいけい)」とは、相手への敬意や礼儀を表して、文書の冒頭に使う日本独特の挨拶語(頭語)です。
「謹んで申し上げます」「丁寧にご挨拶いたします」といったニュアンスが込められており、改まった手紙やビジネス文書の始まりを示します。
- 古くは武家や公家社会で、相手を敬う心を形として表現する目的で使われ始めました。
- 現在も社会的・公的な文書、目上の方への手紙、就職活動や企業へのお礼状など、幅広い場面で使われています。
「敬具(けいぐ)」とは、「拝啓」に呼応して使われる結語であり、「敬ってこれを記す」といった意味合いを持ちます。
文書を丁寧に締めくくることで、最後まで相手への敬意を失わない日本の伝統が表れています。
- 英語の「Yours sincerely」「Sincerely yours」に近い役割ですが、日本語ほど明確なペア表現は少ないのも特徴です。
手紙やビジネスメールでの位置
手紙の場合:
「拝啓」は本文の一行目に、続けて時候の挨拶や主旨を書き始めます。本文が終わった後の1行空けた行頭に「敬具」を記載します。
和文縦書き・横書きにかかわらず、この配置が基本です。
拝啓 陽春の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 …(本文)… 敬具
ビジネスメールの場合:
メール本文の冒頭で「拝啓」、最後の挨拶後に「敬具」を入れます。
ただし、近年のビジネスメールは効率化のため省略される傾向もありますが、正式な案内やお詫び、礼状など改まった内容の時は必ず入れましょう。
拝啓がないのに敬具は?
これは意外と多いNG例ですが、「敬具」だけを使うのは不適切です。
「拝啓」と「敬具」はペアで使うもの。
どちらか一方だけでは“きちんとした文書”とは見なされません。
セットで使うことで、「最初から最後まで相手を尊重している」姿勢が伝わります。
- 「拝啓」が抜けている場合:「拝啓」から書き始めましょう。
- 「敬具」だけ書く癖がついている人は、最初に頭語を確認する習慣を。
敬意を表すための重要性
ビジネスや社会生活において「礼儀」は信頼関係の基盤です。
「拝啓」「敬具」を適切に使うことで、以下のようなメリットがあります。
- 社会人としての“マナー力”をアピールできる
- 目上の人や取引先との信頼構築につながる
- 書類選考や就活でも好印象を与える
日本は「空気を読む」「相手を思いやる」文化が根付いており、形式美を重んじる風土です。
だからこそ、「拝啓」「敬具」は単なる言葉以上に、“気配りの見える化”とも言えます。
拝啓と敬具の使い分け
「拝啓」「敬具」は標準的な組み合わせですが、状況により以下のようなバリエーションもあります。
| 頭語(文頭) | 結語(文末) | 使用シーン |
|---|---|---|
| 拝啓 | 敬具 | 一般的な手紙・メール |
| 謹啓 | 謹白 | より改まった場面 |
| 前略 | 草々 | 急ぎや略式 |
| 拝復 | 敬具/敬白 | 返信時 |
- 「謹啓」「謹白」…重要な取引先や式典の招待状など、より丁寧にしたい場合
- 「前略」「草々」…時候の挨拶を省きたい時(略式のやりとり)
ポイント:相手・目的・時期によって最適な頭語・結語を選びましょう。
ビジネス文書における用法

ビジネスメールでの正しい使い方
現代ビジネスの主戦場はメールですが、「拝啓」「敬具」をどう使えばよいか迷う人は少なくありません。
メールでも、重要な連絡や初対面の相手、正式な案内やお詫びなど、改まった場面では手紙と同じく「拝啓」「敬具」を使うのがマナーです。
- 件名や宛名の直後、本文の最初に「拝啓」と記載します。
- メールの最後の行に「敬具」を入れ、下に自分の名前や署名を添えます。
- カジュアルなやりとりや定型的な業務連絡の場合は、省略しても問題ありません。
- メールは文字が詰まりやすいので、改行や空白行を入れて読みやすく工夫しましょう。
【メール例】
株式会社〇〇 人事部 〇〇様
拝啓 初春の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
先日はご多忙の中、面接の機会をいただき誠にありがとうございました。
(本文略)
敬具
〇〇〇〇
横書きの手紙での注意点
紙の手紙や礼状も、現代では横書きが一般化しています。
その場合も、「拝啓」「敬具」の書き方・位置は縦書きと同じです。
特にパソコンやワープロで作成する場合、一行目に「拝啓」、本文最後の一行下に「敬具」とします。
- 横書きの場合、和文書式に沿って1行あける・余白をつくるなど、視認性にも配慮を。
- 形式を崩さず「拝啓」と「敬具」がセットで並ぶよう注意しましょう。
拝啓 盛夏の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 (本文略) 敬具
一筆書きのポイント
一筆箋や贈答時のメッセージカードなど、短い文章でも礼儀を伝えたい場合は、「拝啓」「敬具」をあえて入れることでぐっと印象がアップします。
たとえば、手土産に添える一言や、異動・転職時のご挨拶状などもこのスタイルが有効です。
- 短文でも、冒頭「拝啓」・結び「敬具」をセットで使うと好印象。
- 改行が難しいときは、1行の中で
拝啓 このたびはお世話になりました。敬具
のようにまとめても可。 - 贈り物に「心ばかりの品をお届けいたします。拝啓 敬具」と一筆入れるだけでフォーマル感が増します。
カジュアルなシーンでどう使う?
ビジネスメール以外や、親しい間柄の場合、「拝啓」「敬具」はやや堅苦しく感じることもあります。
LINEや社内チャット、SNSのメッセージなどでは「こんにちは」「それでは失礼します」といったカジュアルな挨拶で十分です。
- ただし、社内でも社長や重役、外部の方へ送る重要な場面ではフォーマルにしておくと安心です。
- 相手や状況に応じて「どこまで丁寧にするか」を調整しましょう。
実践・例文集
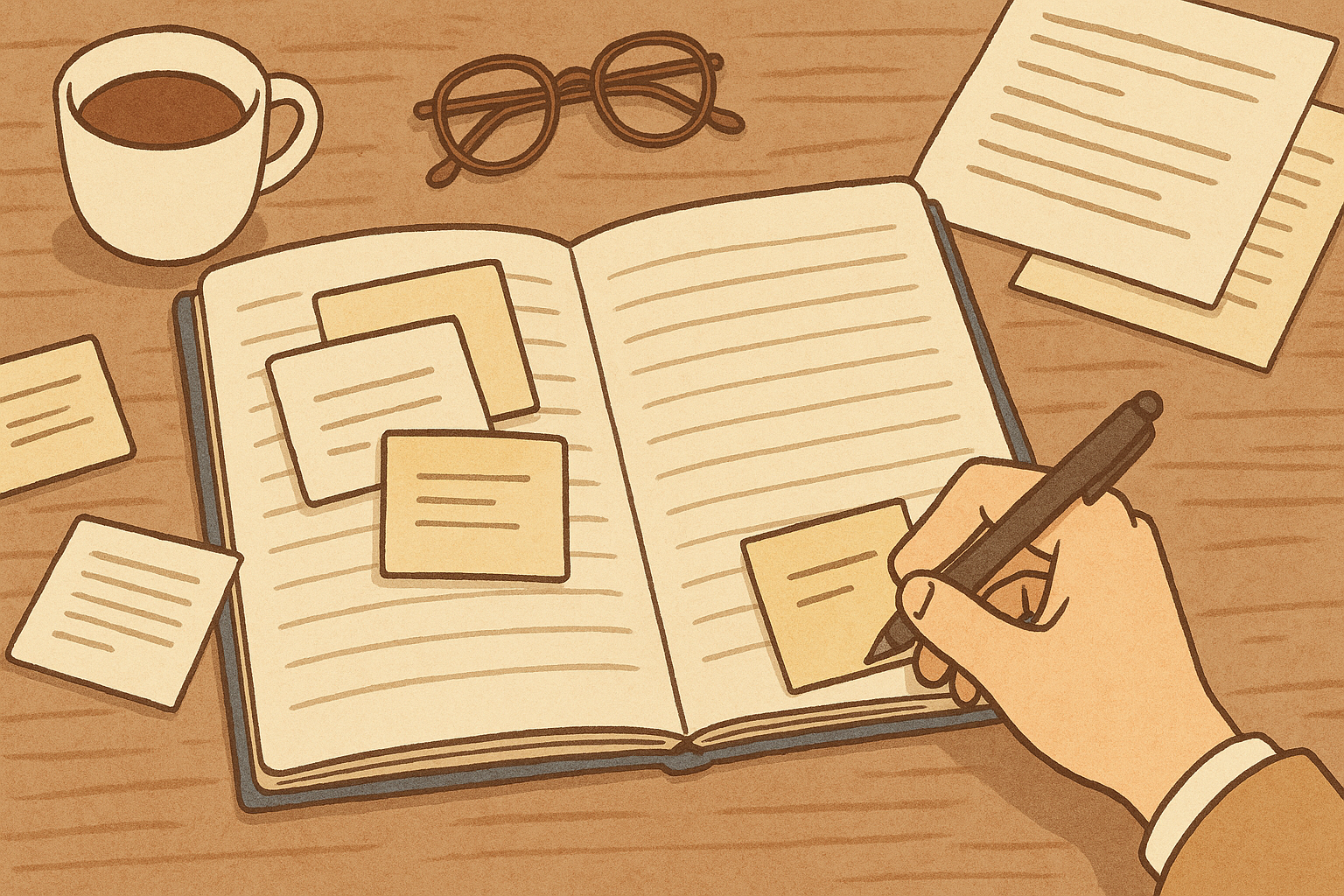
具体的な例文とシーン別主旨
「拝啓」「敬具」を実際にどう使うか。ここでは主なビジネスシーン別の例文とともに解説します。
拝啓 このたびはご多忙の中、ご出席いただき誠にありがとうございました。
今後とも変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
拝啓 先日の件につきまして、ご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます。
今後はこのようなことのないよう、再発防止に努めてまいります。
敬具
拝啓 春暖の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、来る○月○日、弊社主催のセミナーを開催いたしますので、ご案内申し上げます。
敬具
形式の違いとその実用性
紙の手紙では必須ですが、メールやチャットでは省略されることが多い「拝啓」「敬具」。
しかし、公式な案内や、他社との差をつけたい大切な場面では、あえてしっかり使うことで「きちんと感」「信頼感」を印象付けることができます。
- 特に「第一印象を大事にしたい場面」や「公式なやりとり」では、多少時間がかかっても形式美を重視しましょう。
お礼や謝罪の場面での使用法
「拝啓」「敬具」は、感謝や謝罪の気持ちをより丁寧に、真摯に伝えたい場面で特に効果的です。
ビジネスでの信頼関係構築の第一歩は“誠実な言葉選び”から。きちんとした挨拶で相手に好印象を与えましょう。
年賀状など特別なケース
年賀状や暑中見舞い、慶弔など、季節や行事に合わせた特別な頭語・結語が存在します。
年賀状では「謹賀新年」「賀正」など、暑中見舞いでは「暑中お見舞い申し上げます」など、手紙の形式に応じた挨拶を使い、「敬具」は省略するのが一般的です。
- 年賀状の場合:
謹賀新年
旧年中は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
マナーと注意点

使わないべきケースとは?
「拝啓」「敬具」は非常にフォーマルな表現です。そのため、すべてのメールや手紙で使えば良いわけではありません。むしろ場面を選ばず多用すると「堅苦しい」「わざとらしい」「形式的すぎる」とネガティブな印象を持たれることもあります。
- 社内の短い連絡:社内メールや伝達メモ、チャットなど、日々の業務連絡では「拝啓」「敬具」は不要です。
- 親しい関係の手紙:家族や友人、同僚などとの私的なやりとりでは、もっとカジュアルな挨拶(「こんにちは」「それではまた」等)で十分です。
- 即答が求められる場面:緊急時やスピード重視のやりとりでは、本文を簡潔にまとめることが大切です。
例外:同じ社内でも社長や役員へのお詫び、退職の挨拶、フォーマルな招待状などでは「拝啓」「敬具」を使うのが無難です。
失礼にならないためのポイント
「拝啓」「敬具」を使う際は、次の点に注意しましょう。
- 頭語と結語は必ずセットで使う。片方だけでは不自然です。
- 間に主旨や本文をきちんと書く。挨拶文だけで終わると「中身がない」と思われます。
- 誤字脱字や敬語の誤用を避ける。特に目上の方や取引先には細心の注意を払いましょう。
- ネットで拾った文例やテンプレの丸写しは避ける。一言でも自分の気持ちや相手への配慮を加えることが大切です。
書き終えたら一度声に出して読んでみる・第三者にチェックしてもらうのも有効な確認法です。
相手によって調整が必要な場合
「拝啓」「敬具」は万能ではありません。
相手の立場や年齢、関係性、手紙やメールの目的に合わせて柔軟に使い分けましょう。
- 目上の人・初対面の取引先:よりフォーマルに、時候の挨拶や本文も丁寧な表現を。
- 同僚や部下、親しいお客様:簡略化した挨拶や、より親しみのある表現も選択肢に。
- 社内外のお詫びや謝意:いつもより丁寧なフォーマットを心がける。
どんな相手でも共通して大切なのは、「気配り」と「誠実さ」です。形だけにとらわれず、相手の立場や気持ちを思いやる姿勢が信頼を生みます。
日本語の敬語における基本的な理解
「拝啓」「敬具」は、謙譲語・尊敬語・丁寧語と並び、日本語の敬語文化を象徴する表現です。
これらをうまく組み合わせることで、文章全体に「きちんと感」「安心感」「日本語の美しさ」を与えることができます。
- 「拝啓」は謙譲語的な意味合いがあり、書き手がへりくだって相手に挨拶する形。
- 「敬具」は、敬って文を締めくくる結語。相手への敬意と感謝の気持ちを強調します。
- 本文でも、「ご高配」「ご健勝」「ご指導賜りますようお願い申し上げます」など、丁寧な日本語表現を意識しましょう。
例:
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
(本文)
今後ともご高配を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
言い換え表現と活用法
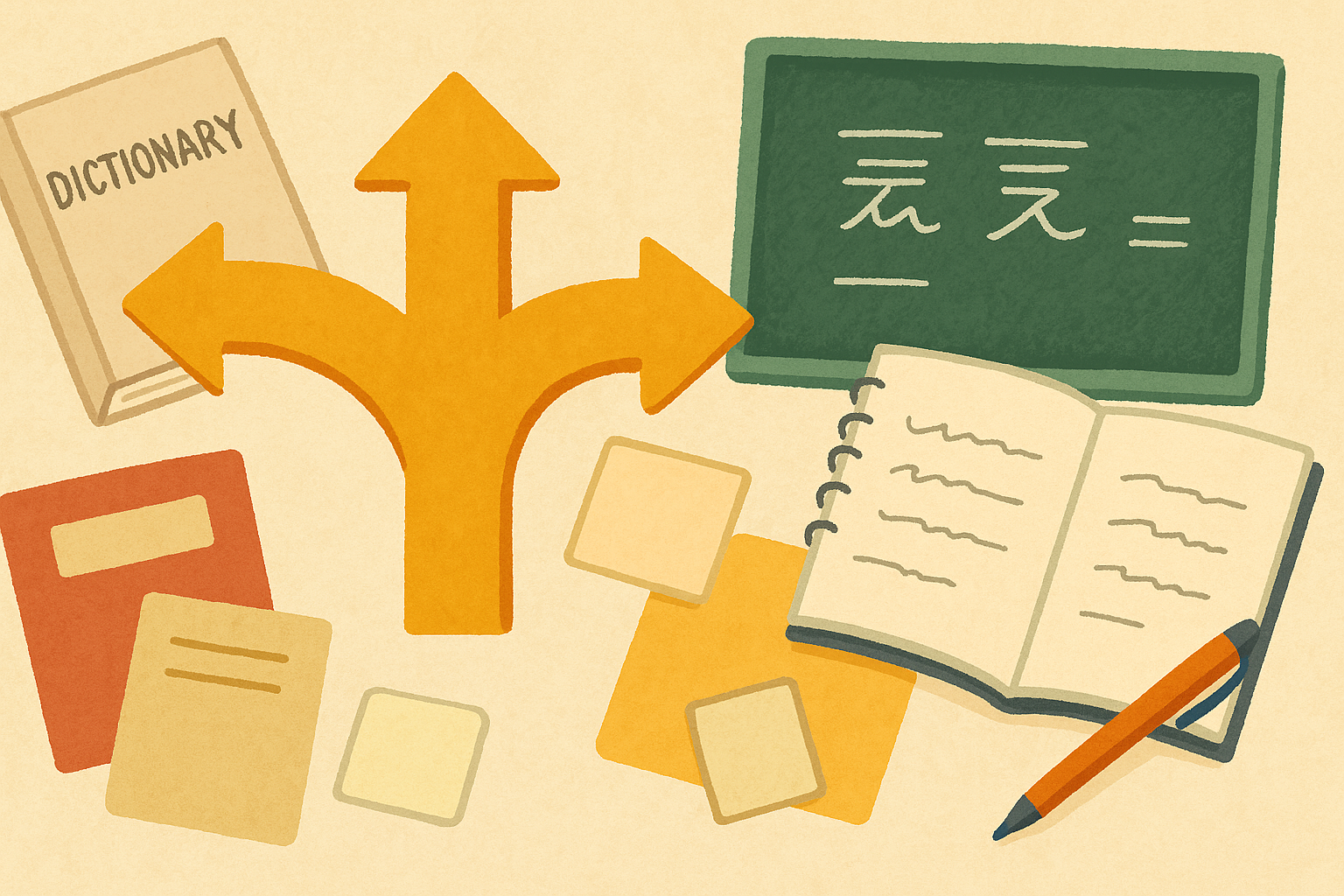
謹啓・敬白などの使い方
「拝啓」「敬具」以外にも、手紙やビジネスメールにはさまざまな頭語・結語の組み合わせがあります。
シーンや相手によって使い分けることで、よりきめ細やかな心配りや敬意を表現できます。
| 頭語(冒頭) | 結語(結び) | 主な使用シーン |
|---|---|---|
| 拝啓 | 敬具 | 一般的な手紙・ビジネス文書 |
| 謹啓 | 謹白 | 公式な案内状や重要なお詫び |
| 前略 | 草々 | 時候の挨拶を省略する略式、親しい相手や急ぎの連絡 |
| 拝復 | 敬具/敬白 | 返信や返書の場合 |
- 謹啓・謹白:「拝啓」「敬具」よりさらに丁寧・改まった表現で、儀礼的な文書や公式な通知、お悔やみの手紙などで使われます。
- 前略・草々:略式や急ぎのやりとり、時候の挨拶を省略したい場合に便利です。
- 拝復:返事や返信の場合の頭語。「貴信拝受いたしました」などと続きます。
頭語と結語は必ずセットで使い、場面・相手によって最適なものを選びましょう。
ビジネスシーンでの便利な表現
ビジネスメールや手紙の現場では、「拝啓」「敬具」以外にも知っておくと役立つ便利な表現があります。
- メール冒頭の「お世話になっております」「日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます」などを併用すると、より丁寧な印象に。
- 返信時には「拝復」「ご返事申し上げます」といった表現を。
- 社内外やカジュアルなやりとりでは「こんにちは」「失礼します」など簡潔な挨拶も可。
フォーマルとカジュアルを上手に使い分け、相手との距離感・信頼感を調整しましょう。
英語での表現と文化的違い
英語にも「拝啓」「敬具」に相当する表現がありますが、日本語ほど厳格なルールやセット表現はありません。
- 冒頭:「Dear Sir/Madam」「To whom it may concern」など
- 結び:「Sincerely」「Best regards」「Yours faithfully」など
日本のビジネスメール文化のように「冒頭・結びの定型」を細かく使い分ける習慣はあまりなく、要点・結論を簡潔に伝えるのが主流です。
文化的な背景を理解し、海外の相手には分かりやすく、冗長になりすぎない表現を心がけましょう。
まとめと今後の活用法

正しい使い方がもたらす印象
「拝啓」「敬具」などの丁寧な挨拶を正しく使えるかどうかで、ビジネスシーンでの第一印象が大きく変わります。
- 信頼感:書き手の礼儀・誠実さが伝わり、安心してやりとりできる相手だと思われます。
- 日本語力・教養:社会人としてのスキル・教養が問われる場面で大きなアピールポイントになります。
- 印象の差別化:多数のメールや手紙の中でも、きちんとした挨拶ができることで「できる人」として印象付けられます。
逆に、「拝啓」「敬具」を誤用したり、どちらかだけ使ったりすると「マナーがなっていない」と評価される可能性もあるため注意が必要です。
ビジネスコミュニケーションにおける重要性
社会人の基本は「コミュニケーション」です。
中でもビジネスメールや手紙は、あなた自身の分身となり、取引先や上司、同僚との信頼関係を築くための大切なツールです。
「拝啓」「敬具」を正しく使いこなすことは、社会人・ビジネスパーソンとしての信頼・評価を大きく左右します。
- 新規取引や大切な交渉の場では「きちんと感」で差がつく
- 社内外のあらゆる書類・文書でも“礼儀”は重要
ケーススタディの振り返りと実践提案
本記事で紹介した多様な事例・表現を、日々のメールや手紙で実際に試してみてください。
- まずはフォーマルな案内文やお礼状・謝罪文で「拝啓」「敬具」をきちんと使うことからスタート
- 相手や目的によって「謹啓」「謹白」「前略」「草々」なども活用
- 社内や他社の好印象な文例をメモしておくと、いざというとき役立ちます
正しいマナーは、相手への最大の敬意であり、あなた自身の価値を高める武器です。
迷ったときはこの記事を読み返し、まずは“挨拶”から一歩踏み出してみましょう。
ビジネスマナーの基本「拝啓」「敬具」を、あなたの信頼と成果につなげてください!