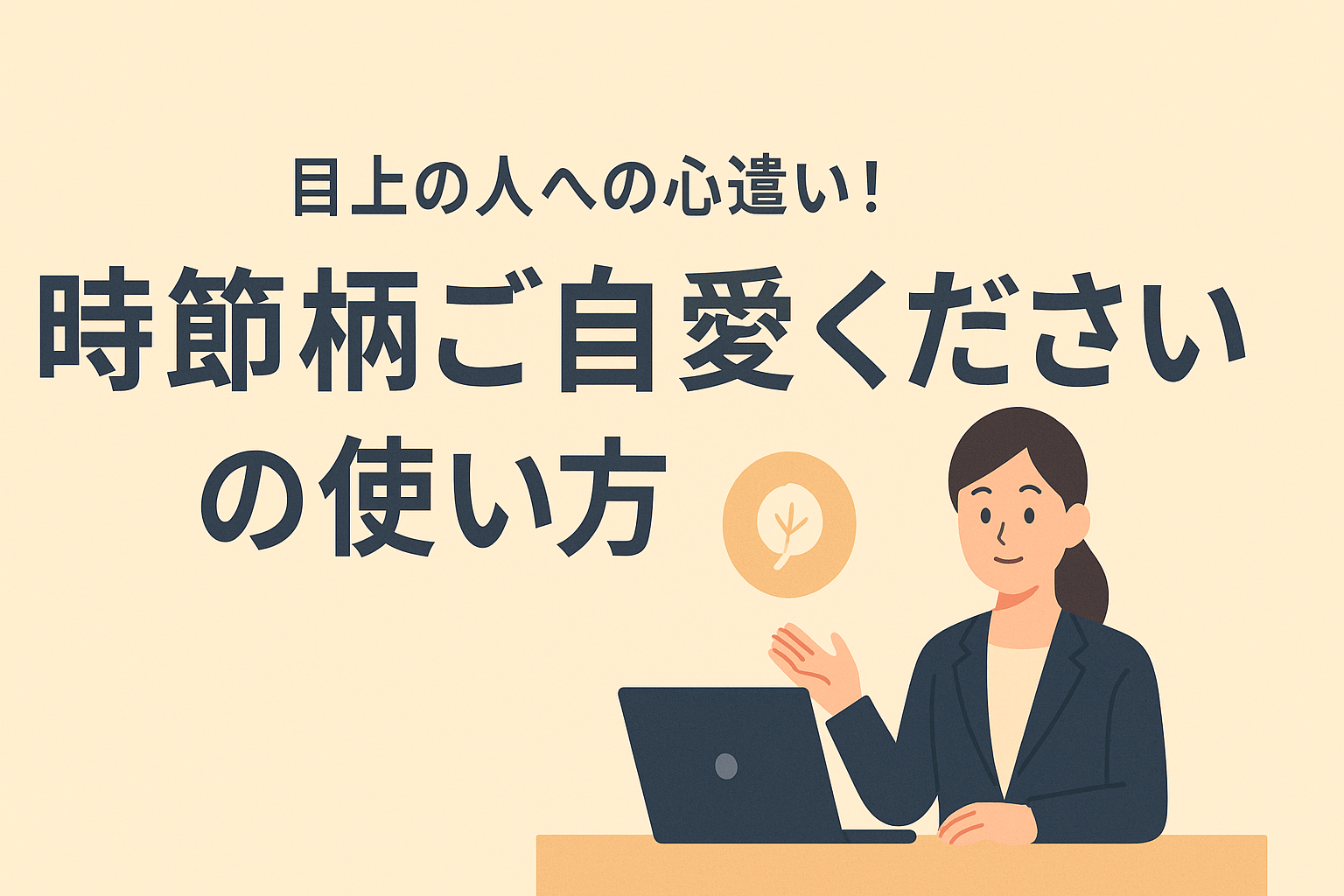日常生活の中で、つい「早く終わらせたい」「近道をしたい」と思うことはありませんか?
でも、そんなときこそ「急がば回れ」という言葉が大切になります。
このことわざは、焦らず確実に進むことが、最終的に成功への一番の近道であるという昔からの知恵を伝えています。
この記事では、「急がば回れ」の意味や由来、使い方を小学生にも分かりやすく紹介します。
さらに、日常や勉強の中で使える例文、英語での言い回し、遊びながら学べる方法まで、楽しく理解できるように解説していきます。
急がば回れとは?このことわざの基本を知ろう

急がば回れの意味とは?
「急がば回れ」とは、急いでいるときこそ、近道ではなく安全で確実な方法を選ぶ方が結果的に早く目的を達成できるという意味のことわざです。
これは「焦る心を落ち着かせ、遠回りでも正しい道を選ぶことの価値」を教えてくれる大切な教えです。
この言葉は、ただ“ゆっくり進もう”という意味ではなく、「失敗を防ぎ、最終的にゴールへ確実にたどり着くための知恵」でもあります。
たとえば、宿題を早く終わらせようとして間違いだらけになるよりも、少し時間をかけて丁寧に進めたほうが結果的に早く終わることがあります。
そうした日常の中でこそ、この言葉の本当の価値が分かります。
つまり、焦って雑に進むよりも、落ち着いて丁寧に行動したほうがうまくいく、という教えを伝えています。
これは勉強だけでなく、スポーツや友達との約束、家のお手伝いなど、あらゆる場面で生きる考え方です。
急がば回れの語源を探る
この言葉の由来は、室町時代の歌人・宗長(そうちょう)が詠んだ和歌からきています。
「急がば回れ、瀬田の長橋」
琵琶湖を渡る際、舟で近道を行くよりも、橋を渡ったほうが安全で確実だという意味です。
舟で渡ると天候や波に左右される危険がありますが、橋を渡れば少し時間はかかっても安心して目的地に着くことができます。
このように、危険を避けて安全な道を選ぶ方が、結果的に早いという考え方が昔から伝えられているのです。
また、この考えは日本人の「慎重さ」や「計画性」を大切にする文化にもつながります。
無理をせず、着実に進むことが信頼や成果につながるという価値観です。
急がば回れの読み方と使い方
「急がば回れ(いそがばまわれ)」と読みます。
使うときは、何かを急いで失敗しそうな人に注意や助言として使います。
学校の先生や保護者が子どもに使う場面が多いですが、友達同士でも「落ち着いてやろう」という意味で使えます。
例:
- 「テスト勉強を一夜漬けでするより、毎日少しずつやったほうがいいよ。急がば回れだね。」
- 「近道は工事中で危ないから、急がば回れだよ。」
- 「焦って絵を描いたらぐちゃぐちゃになっちゃった。今度は急がば回れだね。」
急がば回れの類語と対義語について
類語:
- 「石橋を叩いて渡る」(慎重に行動すること)。失敗を恐れ、確認を重ねて安全な方法を選ぶという意味です。
- 「安全第一」。安全を最優先に考えることで、焦らず落ち着いて進む姿勢を示します。
- 「千里の道も一歩から」。大きな目標も一歩ずつ進むことが大切という教えで、急がば回れの精神と共通しています。
これらの類語は、いずれも「焦らず確実に進むこと」「安全・丁寧さを重視すること」という共通点があります。
場面によって言い換えることで、ことわざを使いこなす幅が広がります。
対義語:
- 「無鉄砲」や「短気は損気」(焦って行動して損をすること)。考えなしに突っ走ると、結果的に時間を失うという意味です。
- 「急いては事を仕損じる」。急ぐあまり失敗してしまうという警告の言葉で、急がば回れの反対の立場から同じ教えを伝えています。
これらを比べると、「急がば回れ」は単なる慎重さではなく、目的を達成するための最善の方法を冷静に選ぶ知恵であることがわかります。
急がば回れの例文集
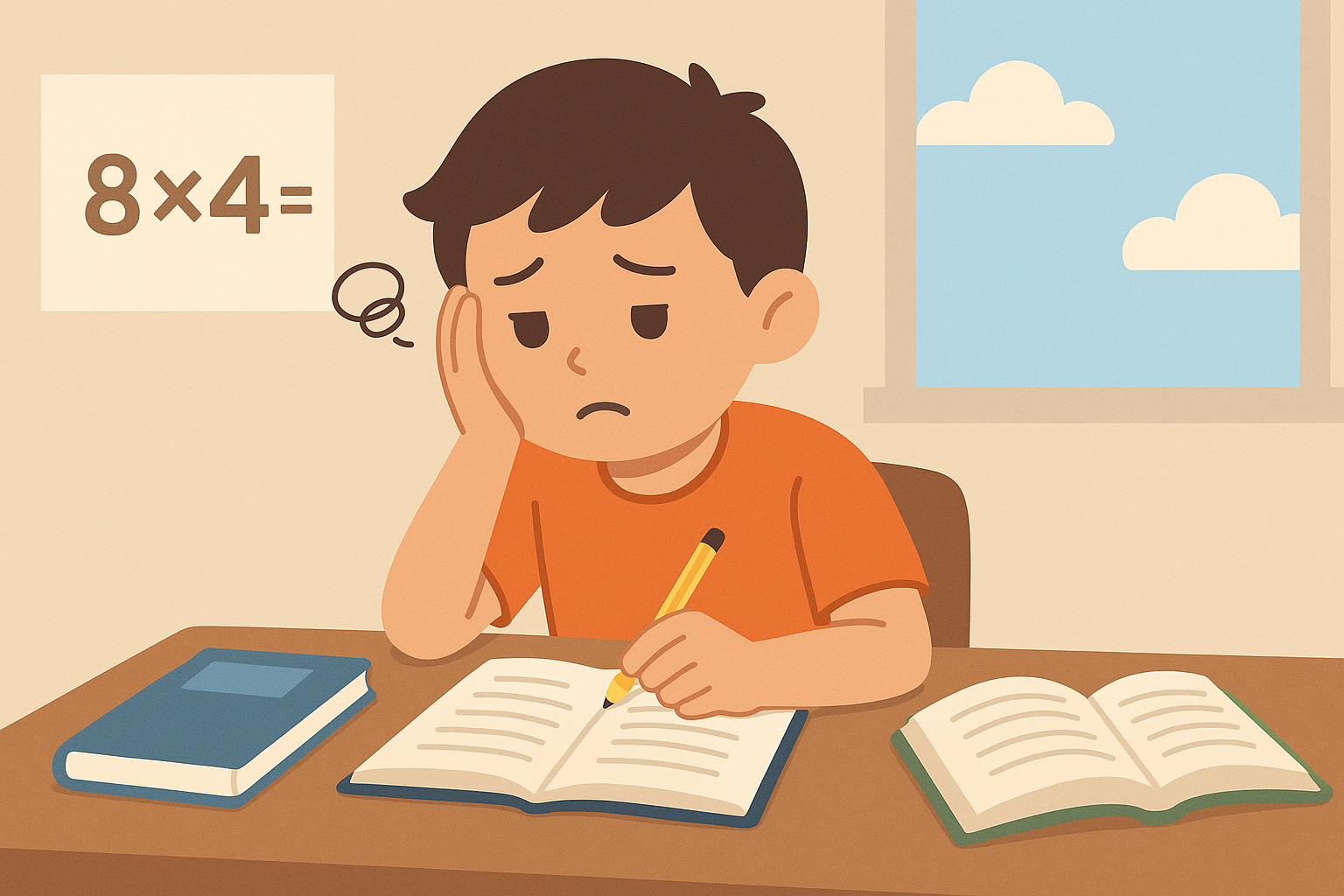
小学生向けの短い文での使い方
- 「宿題を早く終わらせようとして間違えた。やっぱり急がば回れだ。」
- 「焦らずにゆっくり書いたほうがきれいな字になる。急がば回れだね。」
- 「体育の練習で焦って走ったら転んじゃった。次は急がば回れを思い出そう。」
- 「料理を急いで作ったら味が薄かった。急がば回れってこういうことだね。」
これらの例文は、身近な体験を通してことわざの意味を自然に理解できるようにしています。
短くても状況が具体的なので、小学生にもイメージしやすいです。
「急がば回れ」を使った会話例
先生:「漢字テストで間違いが多いね。もっと早く終わらせようと思った?」
生徒:「はい、急いで書いたら間違えちゃいました…」
先生:「急がば回れ。丁寧に書くほうが結果的に早く覚えられるよ。」
生徒:「なるほど、次はゆっくり書きます!」
友達同士の会話例:
A:「夏休みの自由研究、早く終わらせようとしたらうまくいかなかったんだ。」
B:「それは急がば回れだね。少しずつ調べたほうが結果が良かったかも。」
A:「うん、次は計画を立ててやってみる!」
このように、日常の中でも使える自然な会話で「急がば回れ」の意味を体感できます。
急がば回れの例文:知恵袋からの抜粋
- 「掃除を手抜きしたら、あとでやり直すことになった。まさに急がば回れです。」
- 「慌てて答えたら間違えた。急がば回れという言葉を思い出した。」
- 「焦って工作をしたら接着剤が乾かずに壊れた。ゆっくりやればよかったと反省した。」
- 「朝の準備を急ぎすぎて忘れ物をした。急がば回れの大切さを実感しました。」
これらの例は、現実的な場面から学べる“教訓”として役立ちます。
焦るよりも落ち着いて取り組むことが、結局は一番の近道であるというメッセージを具体的に感じ取れる内容になっています。
急がば回れに似たことわざ

他のことわざとの違い
「石橋を叩いて渡る」も似ていますが、これは慎重さを重視することわざです。
たとえば、危険が少しでもあるときに十分に確認してから行動する、という意味合いが強いです。
一方、「急がば回れ」は効率を考えた慎重さを意味し、結果的に成功や目的達成を早めるための冷静な判断を含みます。
つまり、「石橋を叩いて渡る」が“慎重すぎる行動”を示すこともあるのに対し、「急がば回れ」は“賢い行動”を促すポジティブな言葉といえます。
他にも、「七転び八起き」や「備えあれば憂いなし」も、時間や努力を惜しまない姿勢を表しています。
焦らずに地道に取り組むことが、最終的には成功につながるという点で、これらも急がば回れと深い関連があります。
急がば回れの使い方と他の言葉との関連
「三人寄れば文殊の知恵」「転ばぬ先の杖」なども、急がば回れと似た教えがあります。
どれも「慌てず、準備や相談をして行動する大切さ」を伝えています。
これらを組み合わせて使うと、より深みのある表現になります。
たとえば、「転ばぬ先の杖で準備しておけば、急がば回れで安全に進めるね」といった使い方をすると、慎重さと計画性を両方伝えることができます。
また、現代社会でも「急がば回れ」の精神はさまざまな場面に応用できます。
スポーツでは無理に力を入れるよりもフォームを整えることが大事、勉強では暗記より理解を優先する方が結果的に効果的です。
このように他のことわざや考え方と結びつけることで、日常生活全体に生きる知恵として活かせます。
急がば回れを学ぶための効果的な方法
- 絵本や漫画でことわざを覚える。登場人物の行動と結果を通じて、意味が感覚的に理解できます。
- ことわざカルタを使って遊びながら覚える。声に出して読むことで、記憶に残りやすくなります。
- 日常生活の中で実際に使ってみる(例:「今日は急がば回れだね」)。家族や友達との会話に取り入れると、自然に定着します。
- 学校の授業や作文で使う練習をする。自分の体験と結びつけて書くことで、ことわざの意味をより深く理解できます。
- 動画やアニメで視覚的に覚える。物語の中でどう使われているかを見ると、使い方の幅が広がります。
急がば回れを使った学習法

イラストを用いた理解の助け
ことわざを絵で見ると、意味が分かりやすくなります。
たとえば、「近道を行く人が川に落ちる」「遠回りして橋を渡る人が無事に進む」といったイラストで理解を深めましょう。
さらに、絵の中にキャラクターの表情や行動を描くことで、子どもたちが感情的に共感しやすくなります。
学校の授業や家庭学習で絵日記のようにことわざを描く練習をすると、自然に記憶に残ります。
また、絵と一緒に短い説明文やセリフを加えると、言葉の使い方まで身につきます。
遊び感覚で学ぶ急がば回れ
- ことわざビンゴやカルタで遊びながら覚える。カードの絵や例文を見て意味を当てるゲームにすれば、家族や友達とも楽しめます。
- クイズ形式で「これは急がば回れの例?」「それとも違う?」と判断するゲームをする。正解の理由を話し合うことで、思考力や説明力も育ちます。
- ことわざを題材にした劇や紙芝居を作る。役になりきって言葉の意味を演じると、身体で覚えられます。
- スマートフォンやタブレットの学習アプリを活用して、音声や動画でことわざを聞くのもおすすめです。視覚と聴覚を使うことで理解が深まります。
安全・仕事に活かす急がば回れ
大人の世界でも「急がば回れ」は重要です。
安全確認を怠らない、計画を立てて行動するなど、社会でもこの考え方が活かされています。
さらに、ビジネスでは「短期的な利益よりも信頼を築く」ことが長期的な成功につながります。
プロジェクトやチームワークの場面でも、焦って結論を出すより、準備を整えてから行動する方が良い結果を生みます。
また、家庭や地域活動でも「焦らず準備を整える」「一度立ち止まって確認する」といった姿勢がトラブル防止につながります。
つまり、「急がば回れ」は子どもだけでなく大人にも通じる“生き方の知恵”なのです。
急がば回れを英語で表現してみよう

急がば回れの英語訳とその使い方
英語では、次のように表現されます:
- More haste, less speed.(急ぐほど、かえって遅くなる)
- Slow and steady wins the race.(ゆっくりでも着実な人が勝つ)
- Take your time.(時間をかけて落ち着いてやりなさい)
- Haste makes waste.(急ぎは無駄を生む)
どれも「焦らず確実に進むことが大切」という意味を持ち、日常会話やビジネスでもよく使われます。
「急がば回れ」と同じように、英語圏でも“落ち着き”や“計画性”を重視する考え方が広く浸透しています。
英語での会話例
A: You’re typing too fast. You’ll make mistakes.
B: Yeah, you’re right. More haste, less speed!
A: I guess I should slow down. Slow and steady wins the race, right?
B: Exactly. It’s better to take your time and do it right.
このように、英語でも「急がば回れ」に近い表現を使うと、落ち着いた行動や慎重な判断を促すことができます。
学校での会話、仕事の打ち合わせ、スポーツ指導など、さまざまな場面で応用できます。
英語表現との違いを探る
日本語の「急がば回れ」は、危険や失敗を避けるための慎重さを強調します。
一方、英語の表現は「ゆっくりでも確実に成功する努力」を重視する点が少し異なります。
さらに英語では「結果を急がない」「自分のペースを大切にする」といったポジティブなメッセージが込められています。
また、ことわざの背景にも文化の違いがあり、日本では“安全・慎重”を重視するのに対し、英語圏では“継続的な努力”や“自分のリズムを保つ”ことが美徳とされています。
まとめ

「急がば回れ」は、焦らず着実に進むことの大切さを教えてくれる、昔からの知恵です。
この言葉は、努力や忍耐、そして慎重な判断がどんな状況でも成功へ導くことを思い出させてくれます。
一見遠回りに思えても、確実な道を選ぶことで結果的に早く、しかも確実に目標へたどり着くことができるのです。
また、「急がば回れ」は学校生活だけでなく、友達との関わり方や家庭での行動、将来の仕事にもつながる“生きる力”のひとつです。
失敗してもすぐに諦めず、落ち着いてやり直す姿勢を持つことが、本当の意味での「賢い選択」につながります。
小学生のうちからこの考え方を身につけておくことで、勉強や生活の中で失敗を減らし、長い目で見て成功へ近づくことができます。
さらに大人になっても、「焦らず確実に行動する」という心構えは、多くの場面で自分を助けてくれることでしょう。