ビジネスメールや手紙、スピーチなどでよく使われる「御礼申し上げます」。
一度は目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし「読み方は正しいのか」「お礼との違いはあるのか」「どの場面で使うべきか」と迷う人も少なくありません。
本記事では「御礼申し上げます」の正しい読み方や意味、使うべきシーン、表記方法、さらには英語表現まで徹底解説します。
社会人として知っておくと必ず役立つ表現ですので、ぜひ最後までご覧ください。
「御礼申し上げます」とは?

御礼申し上げますの正しい読み方と発音
「御礼申し上げます(おんれいもうしあげます)」と読みます。
ビジネスシーンや改まった場面でよく使われる表現で、相手に深い感謝を伝える際に用いられる非常に丁寧な言葉です。
「おれいもうしあげます」と誤って読まれることもありますが、正しくは「おんれい」です。
ここで重要なのは「御」という接頭語が丁寧語として機能しており、感謝の対象を一層引き立てる役割を果たしているという点です。
また、発音の際には「おんれい」の「ん」を明確に発声することで、改まった雰囲気が伝わりやすくなります。
アナウンサーや司会者などは、この表現を特に丁寧に発音することで聞き手に誠意を伝えています。
「御礼申し上げます」の意味と背景
「御礼申し上げます」は「感謝の気持ちを改めてお伝えいたします」という意味を持つ敬語表現です。
単なる「ありがとうございます」よりも格式が高く、儀礼的・正式な場で好まれる言葉です。
もともとは武家社会や公家社会における礼儀作法の中で培われた表現で、手紙や口頭の挨拶において頻繁に用いられてきました。
江戸時代の往来文書や明治期のビジネス文書にも登場しており、長い歴史の中で社会人の常識的な言葉として根付いたといえます。
今日ではビジネスメールや講演、式典などさまざまなシーンで用いられ、社会的な信頼や敬意を表す便利な定型句として位置づけられています。
「御礼申し上げます」はどんなシーンで使うのか?
- ビジネスメールの結びとして、取引や商談後に相手へ深い感謝を伝えるとき
- 結婚式や葬儀など、人生の節目で参列者や関係者に対して敬意を示すとき
- 講演やイベント後のスピーチで聴衆に対し、心からの謝意を伝えるとき
- お歳暮やお中元のお礼状など、季節の挨拶に感謝を込めるとき
- 学会や研究発表後に協力者・参加者へ感謝を述べるとき
このように、改まった感謝を伝える必要があるシーンで用いられます。
単なる「ありがとう」では軽く感じられる場面において、「御礼申し上げます」を使うことで文章や発言全体が格調高くまとまり、相手に誠実な姿勢が伝わります。
「御礼申し上げます」とその使い方
ビジネスシーンにおける御礼申し上げますの使用例
「このたびはご協力いただき、心より御礼申し上げます。」のように、顧客や取引先へ深い感謝を伝える定型文として利用されます。
文章の結びに添えることで、誠実な印象を与えます。
さらに具体的には、契約成立後の挨拶メールや、セミナー・イベント終了後の参加者へのお礼、取引先への訪問後のフォローアップメールでも定番表現として使われています。
特に、商談の結果にかかわらず感謝を伝える場合に用いると、相手に対して信頼感や誠意を強調できます。
また、長期的な取引関係を築くうえで、こうした一言が良好な関係維持に大きな役割を果たします。
口頭でのスピーチにおいても、「本日はご足労いただきまして厚く御礼申し上げます」とすることで聴衆への敬意を伝えることができます。
親しい友人や家族へのカジュアルなお礼
親しい関係では「御礼申し上げます」は硬すぎる印象を与えるため、「ありがとう」「感謝します」の方が自然です。
友人間で使うと距離を感じさせる場合があるため注意が必要です。
たとえばプレゼントをもらったときや日常的な手助けに対しては、シンプルな「ありがとう」の方が温かみが伝わります。
ただし、結婚式や人生の節目など改まった場で親族に感謝を伝える場合は、あえて「御礼申し上げます」を用いることで礼儀正しさを演出することも可能です。
カジュアルさとフォーマルさを状況に応じて切り替えることが大切です。
手紙での御礼申し上げますの適切な表現
手紙や挨拶状では「ご多忙のところご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。」のように、前置きや文脈に合わせて用いると自然です。
特に慶弔や年賀状の場面で定型的に使われます。
さらに、ビジネスレターや招待状への返信などでも用いられ、「まずは略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます」という表現は定番です。
手紙文化が重んじられる日本社会では、文字に残る形での感謝は相手の記憶に残りやすく、社会的信頼を築くうえで極めて有効です。
御礼とお礼の違いとは?
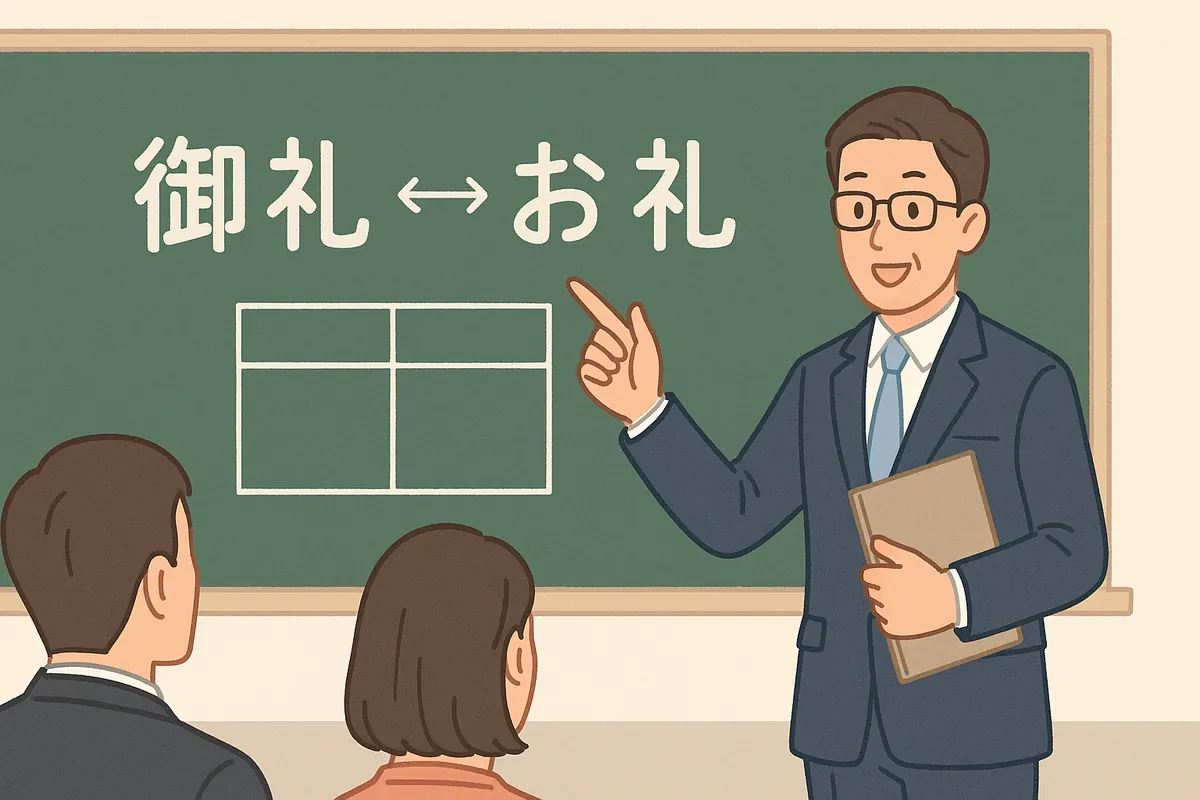
言葉の使い分け:御礼 vs お礼
「御礼」は敬語的・儀礼的な表現で、フォーマルな文章や挨拶で使われます。
一方「お礼」は口語的で日常的な感謝表現です。
例えば「お礼を言う」は自然ですが、「御礼を言う」はやや堅苦しい印象を与えます。
また「御礼」は主に文章や公式スピーチにおいて用いられる傾向が強く、「お礼」は口語や日常会話の中で用いられるため、シーンによって適切に使い分ける必要があります。
さらに「御礼」には相手に敬意を込めた意味合いが強調されるため、目上の人や取引先への表現としては適していますが、親しい間柄で使うとよそよそしく感じられることもあります。
類語とそのニュアンスの解説
- 謝意:感謝の気持ちを表す文語的表現で、文章中に登場することが多い
- 感謝申し上げます:同等の敬意を示すがやや柔らかく、ビジネスメールでもよく用いられる
- 厚く御礼申し上げます:感謝の度合いを強調し、改まった挨拶や式典などで多用される
- 深謝いたします:深い感謝の意を示し、謝辞やスピーチで使われることが多い
- 謹んで御礼申し上げます:特に丁重に感謝を述べる際に使う、より格式の高い表現
御礼申し上げますを使った具体例
「このたびのご厚情に対し、心より御礼申し上げます。」といった表現がよく用いられます。
メール・挨拶状・スピーチなど幅広く活用可能です。
さらに「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」や「本日はご臨席いただき、謹んで御礼申し上げます。」といった文例もあります。
場面に応じて強調や丁重さを調整することができます。
例えばビジネスでは「ご指導ご鞭撻を賜り、厚く御礼申し上げます。」、冠婚葬祭では「ご多忙の折にもかかわらずご出席賜り、深く御礼申し上げます。」とすることで、適切かつ効果的に敬意を伝えることができます。
英語での「御礼申し上げます」
直訳:Thank you と御礼申し上げますの違い
「Thank you」はカジュアルからビジネスまで広く使われますが、「御礼申し上げます」はより格式の高い表現です。
直訳ではニュアンスが完全に伝わりにくい点に注意が必要です。
日本語では相手への敬意や謙譲を同時に込めることが可能ですが、英語では単なる「Thank you」では深い敬意や形式的な要素が不足する場合があります。
そのため、より丁寧で改まった表現を選ぶ必要があるのです。
ビジネスで使える英語表現
- I would like to express my sincere gratitude.
- I am deeply grateful for your support.
- Please accept my heartfelt thanks.
- I would like to extend my deepest appreciation.
- I am sincerely thankful for your continued cooperation.
これらの表現は契約締結後、会議終了時、イベント後の挨拶状などフォーマルなビジネス場面で効果的に活用できます。
日本語の「御礼申し上げます」と同様に、単なる感謝以上に礼儀や敬意を伝えることができます。
御礼申し上げますの英語表現の意義
国際ビジネスにおいては、直訳よりも丁寧な表現を選ぶことで相手への敬意が正しく伝わります。
文化的背景を理解した言葉選びが重要です。
たとえば欧米では「Thanks.」と短く済ませることも多いですが、状況に応じて長く丁寧な表現を用いることで、誠意や真剣さを示すことができます。
また、英文メールでは件名に「Appreciation」や「Gratitude」といった単語を入れると、受け手に好印象を与える効果があります。
さらに、国際的な会議や公式スピーチでは「I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude…」といったフレーズを使うことで、日本語の「御礼申し上げます」に近いフォーマルさを伝えることができます。
御礼申し上げますを使った印象

目上の人への敬意の表現
「御礼申し上げます」を使うことで、相手に敬意と感謝を強調できます。
特に役職者や取引先に対して有効です。
加えて、式典や公式の挨拶などでこの表現を用いると、場の雰囲気が一層引き締まり、聞き手に対して丁寧な印象を与えます。
例えば講演会終了時に「本日はご清聴いただき厚く御礼申し上げます」と述べることで、聴衆全体に敬意を表すことができます。
こうした使い方は、社会的地位や立場にかかわらず、言葉遣いを通して相手を大切にする姿勢を示すものです。
ビジネスメールでの受け取り方
受け取った相手に「誠実」「礼儀正しい」という印象を与えます。
ビジネスの信頼関係構築に役立つ表現です。
特に初めての取引や重要な契約に関わる際に使用すると、相手に安心感や信頼を与えやすくなります。
さらに「このたびは多大なるご尽力を賜り、心より御礼申し上げます」といった文例をメールに添えることで、相手に対して感謝が単なる形式的なものではなく、実際の行動や成果に対して向けられていることを明確に示すことができます。
また、社内メールにおいても上司や先輩への感謝の気持ちを伝える際に活用すれば、円滑な人間関係の維持にも効果的です。
誤用を避けるためのポイント
- カジュアルな場面では避ける。友人同士では不自然に感じられるため「ありがとう」を選ぶ方が適切。
- 同じ文中で何度も繰り返さない。多用すると文章全体が冗長に見え、重い印象を与える可能性がある。
- 「御礼を申し上げます」と冗長にしない。「御礼申し上げます」で十分に意味が伝わる。
- 発音を誤らない。「おんれいもうしあげます」が正しく、「おれいもうしあげます」は誤り。
御礼申し上げますの表記方法の解説
漢字、ひらがな、カタカナの使い分け
- 御礼申し上げます:もっとも正式な表記。ビジネス文書や公式の挨拶状に最適。
- お礼申し上げます:やや柔らかく日常的。フォーマルすぎない関係に向く。
- オレイモウシアゲマス:カタカナ表記は特別な演出以外では不自然。
- 御礼もうしあげます(ひらがな混じり):読みやすさを重視した温かみのある表記。
メールや手紙での正しい表記例
「このたびのご厚情に対し、心より御礼申し上げます。」のように、文章の結びに置くのが自然です。
年賀状や暑中見舞いでは「旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます」といった定型文が好まれます。
招待状への返信や慶弔の挨拶状でも「まずは略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます」とすることで改まった気持ちを示せます。
略儀や深謝の使い方との関係
- 略儀ながら御礼申し上げます:形式を簡略化した謝辞。
- 深謝申し上げます:より強い謝意を示す表現。大きな恩義や支援を受けた場合に用いる。
- 謹んで御礼申し上げます:謙虚さと敬意を込めた言い方。公式行事や公的スピーチに最適。
「御礼申し上げます」に関するFAQ

よくある誤りとその正しい使い方
- ×「御礼を申し上げます」 → ○「御礼申し上げます」
- ×「おんれいをもうしあげます」 → ○「おんれいもうしあげます」
- ×「御礼を申しあげます」 → ○「御礼申し上げます」
- カタカナで「オンレイ」と書くのは不適切。
シーン別の適切なフレーズ例
- ビジネス:このたびのご支援に、心より御礼申し上げます。
- 式典:本日はご多忙の中ご臨席賜り、厚く御礼申し上げます。
- 手紙:まずは略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます。
- 季節の挨拶:旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
- イベント後:ご参加いただきました皆様に、心より御礼申し上げます。
理解を深めるために知っておくべきこと
「御礼申し上げます」は単なる形式的な言葉ではなく、相手との関係を円滑にする潤滑油のような役割を果たします。
正しい場面で使うことでビジネスマナーの高さが評価されます。
逆に誤用が続くと信頼を損なう可能性もあるため注意が必要です。
また、「感謝申し上げます」との使い分けを意識することで、文章に柔軟さと奥行きを持たせることができます。
まとめ
御礼申し上げますの重要性の再確認
「御礼申し上げます」は日本語における感謝表現の中でも特に格式が高い言葉です。
単なる挨拶ではなく、相手への敬意や礼儀を示すための強力な手段です。
面接後のメールで「本日は貴重なお時間を頂戴し、厚く御礼申し上げます」と添えるだけで、受け取った側に誠実さや礼儀正しさを印象づけられます。
日常生活やビジネスでの活用法
場面に応じて「御礼申し上げます」「お礼申し上げます」「ありがとうございます」を使い分けましょう。
冒頭で「まずは御礼申し上げます」と書くと積極性を示し、結びで「厚く御礼申し上げます」と書くと文章全体をまとめられます。
活用例の具体的な箇条書き
- 面接後のメール:本日は貴重なお時間を頂戴し、厚く御礼申し上げます。
- 送別会のスピーチ:皆様のご支援とご厚情に、心より御礼申し上げます。
- 社内表彰の挨拶:このような賞を頂戴できましたことに、深く御礼申し上げます。
- 学会や発表後:ご参加いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。
言葉の持つ力を改めて考える
丁寧な言葉選びは、信頼関係の構築や円滑な人間関係に直結します。
「御礼申し上げます」という表現は、その象徴といえるでしょう。
感謝を形にする言葉として受け手に与える心理的効果は大きく、単なる定型句以上の力を持っています。
特に日本文化では、言葉遣いが人柄や誠意を映す鏡のような役割を果たします。
日々のやりとりで「御礼申し上げます」を的確に使う習慣を身につけることは、自分自身の評価や信頼を高めるためにも欠かせません。
学生や一般の人にとっても、この表現を理解し適切に使えることは大きな財産となります。


