 SNS
SNS LINE返信が面倒なあなたへ送る、楽チン対策法
LINE返信が面倒なあなたへ送る、楽チン対策法「LINEの返信がめんどくさい…」。そんな気持ち、決してあなた一人だけではありません。毎日LINEでやりとりするのがつらい、返すのが億劫、やりとりが終わらずストレスが溜まる——。SNS全盛の今、...
 SNS
SNS  ビジネス
ビジネス  ビジネス
ビジネス  心理
心理  SNS
SNS  ビジネス
ビジネス  ビジネス
ビジネス 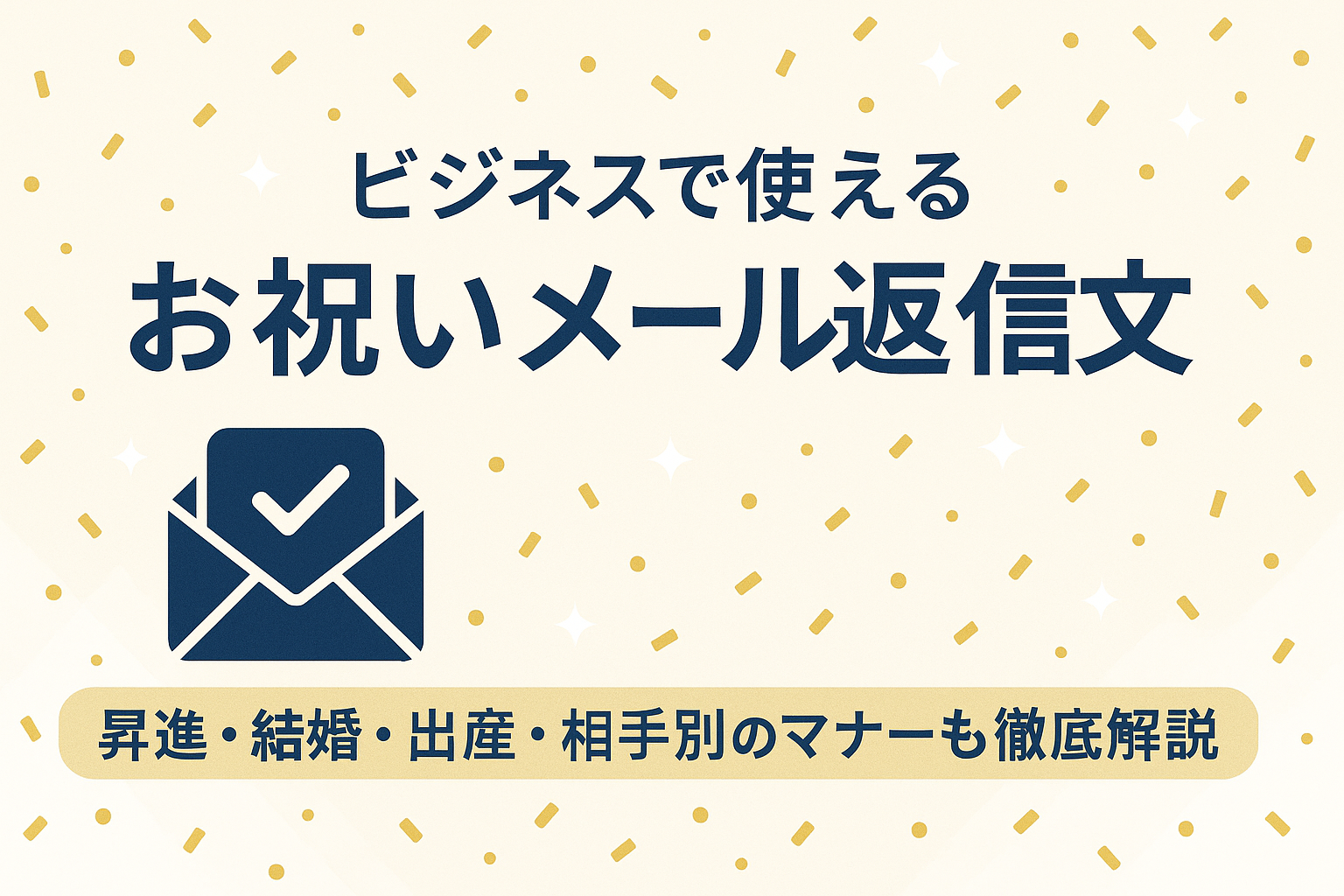 ビジネス
ビジネス  ビジネス
ビジネス 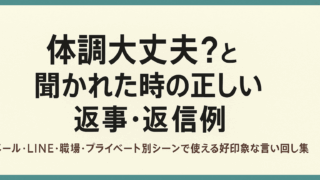 ビジネス
ビジネス