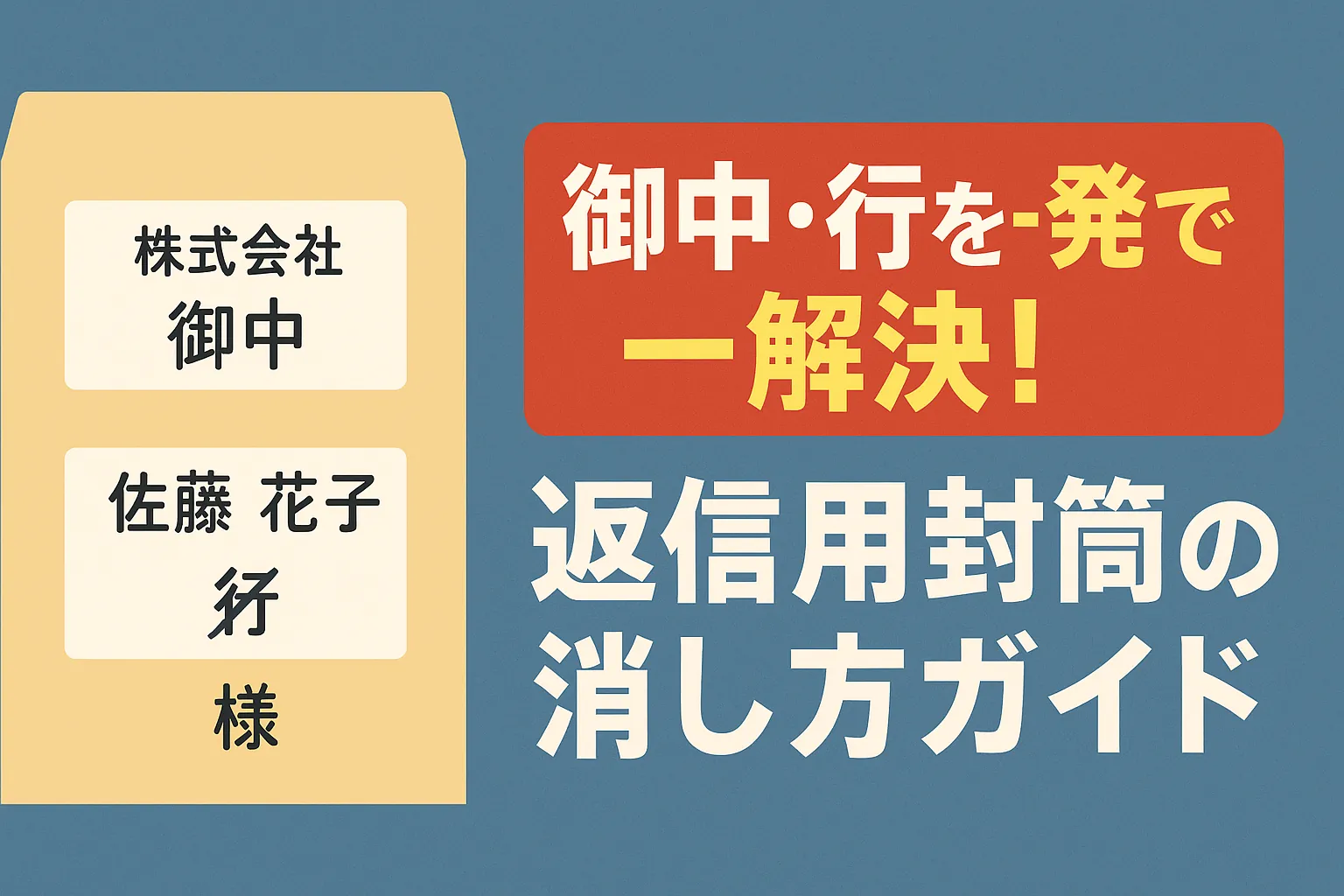ビジネスマナーとして正しく記載・修正する方法を押さえておくことで、印象をぐっと良くできます。
この記事では、御中・行の基本から実際の消し方まで、初心者でも失敗しない手順を徹底解説します。
御中・行を解決するための基本知識

御中の意味とビジネスマナー
「御中」は、会社や団体などの組織宛に使用する敬称です。
個人ではなく部署や組織そのものに宛てる場合に使い、「株式会社○○御中」「○○部御中」と記載します。
また、ビジネス上では、相手の立場に応じた敬称を使い分けることが求められます。
たとえば、取引先企業の担当部署に送る場合は「営業部御中」、学校や官公庁に送る場合は「入試課御中」「総務課御中」といった表記が適切です。
個人名と併用するのは誤りであり、もし担当者が分かっている場合は「○○部 △△様」と書き、「御中」は不要です。
さらに、「御中」はビジネス敬称の中でもやや格式高い表現であり、社外文書や公式な申請書、見積書などにも広く用いられます。
状況に応じて、社内向けやメール文中では「様」などの柔らかい表現に切り替える配慮も大切です。
返信用封筒の基本的な使い方
返信用封筒は、相手が返信しやすいように自分の住所と宛名をあらかじめ記入して送る封筒です。
特に就職活動、転職応募、セミナー申込書、資料請求などでよく使われます。
ビジネスでは「相手の手間を減らす配慮」が評価されるため、返信用封筒を同封する行為自体がマナーの良さを示します。
このとき、宛名に「○○会社 御中」と書くのではなく、自分が受け取る側なので「自分の名前+行」と書くのが基本です。
たとえば「田中太郎 行」や「採用担当 行」といった形です。
また、書体は丁寧に読みやすい楷書体で統一し、郵便番号枠・住所の位置も正確に合わせると印象が良くなります。
万が一、返信先を複数設ける場合は、誤送付を防ぐために封筒ごとに名前や部署を明確にしておくと安心です。
行・消し方に関する一般的なルール
返信用封筒が戻ってくる際、相手は「行」を消して「御中」や「様」に書き換えるのがマナーです。
つまり、自分が送るときには「行」をつけ、相手側がそれを正しい敬称に変える、という流れがビジネス上の暗黙のルールになっています。
この一連のやり取りは、双方の敬意と配慮の表れでもあります。
特に、企業や学校の担当者は受け取った返信用封筒に軽く二重線を引き「行」を消してから「御中」や「様」と書き加えます。
この動作そのものが「相手を立てる」というマナーに通じるため、ビジネス慣習として定着しています。
また、手書きの場合は筆圧や線の角度にも注意し、見た目が乱雑にならないように丁寧さを意識することが大切です。
印刷済みの返信封筒を使う場合も同様で、敬称部分をあらかじめ調整できるようレイアウトを工夫しておくとより好印象です。
返信用封筒の書き方徹底ガイド

縦書きと横書きの使い分け
封筒が縦型の場合は縦書き、横型の場合は横書きで統一します。
ビジネス文書では縦書きが主流ですが、カジュアルな企業や採用関連では横書きも増えています。
縦書きは格式があり、フォーマルな印象を与えるため、役所や官公庁、企業の総務部宛てなどで多く使用されます。
一方で横書きは現代的で読みやすく、特にIT企業やデザイン業界などでは好まれます。
どちらを採用する場合でも、文面の方向性を封筒全体で統一することが重要です。
また、差出人や宛名の位置も文書の流れに合わせて自然に見えるよう配置し、書体も統一するとプロフェッショナルな印象になります。
宛名と敬称の正しい記載法
宛名欄には「○○株式会社 御中」または「○○部 △△様」と記載します。
返信用封筒の場合、自分の名前の後に「行」または「宛」をつけておくのが一般的です。
たとえば、採用試験で提出する書類の返信用封筒では「山田花子 行」と記載します。
これにより相手側が返信時に「行」を二重線で消し、「御中」または「様」と書き換えやすくなります。
もしも部署名が長い場合は改行して整え、見やすく配置しましょう。
特に宛名は封筒の中央に大きく、左右のバランスを意識して書くと印象が良くなります。
また、「御中」と「様」を併用しないよう注意が必要です。
どちらを使うべきか迷った場合は、宛先が個人であれば「様」、組織・部署であれば「御中」が原則です。
自分の住所の位置と書き方
封筒の左下に自分の住所・氏名を明記します。
郵便番号枠がある場合は正確に記入し、縦書きの際は番地などの数字も縦書きでそろえましょう。
郵便番号は赤い枠に丁寧に書き込み、数字がかすれないよう気をつけます。
住所は都道府県から番地まで省略せず書き、建物名や部屋番号も明記します。
ビル名が長い場合は2行に分けて整えると美しくなります。
自分の名前は住所より少し大きめの字で、受け取る人がすぐに確認できるようにします。
特にビジネスの返信用封筒では、読みやすさと清潔感が印象を大きく左右します。
必要に応じて差出人の肩書(例:「株式会社△△ 営業部」)を添えると、より丁寧な印象を与えられます。
一般的な返信用封筒のサイズと印象
ビジネスでは長形3号(120×235mm)が標準サイズです。
A4三つ折りがぴったり入り、スマートな印象を与えます。
色は白または薄いグレーが無難ですが、用途に応じてクリーム色や淡いブルーを選ぶと柔らかい印象を与えることもできます。
封筒の紙質は厚めの上質紙を選ぶとシワになりにくく、信頼感を高めます。
また、返信用封筒には切手をあらかじめ貼っておくのがマナーです。
特に企業や官公庁宛ての場合、84円切手(定形郵便)を貼っておくとスムーズです。
封筒の印象は、書き手の誠実さを伝える小さな名刺のような役割を持っています。
表面だけでなく、裏面の封じ部分も整えて折り目を揃えると、よりプロフェッショナルな印象になります。
消し方の具体的な手法

二重線を用いた消し方の流れ
- 「行」または「宛」の文字に斜めの二重線を引きます。線は右上から左下方向に軽く、一定の角度で引くと美しく仕上がります。
- その上または横に「御中」または「様」を書き加えます。このとき、行間や文字のバランスを意識し、字の中心がずれないように丁寧に配置します。
- 線は軽く、字が読める程度にすることで丁寧な印象になります。あまり濃く引くと乱雑に見えるため、筆圧を一定に保つことがポイントです。
- ペンは黒のボールペンまたは万年筆を使用し、インクのにじみを防ぐために書く前に紙面の油分を取り除くとより綺麗に仕上がります。
- 消した部分の下に小さく「御中」や「様」を添えることで、整った印象になります。特に公式文書の場合は定規を使用し、線の長さを揃えると美しく見えます。
失礼にならない消し方のポイント
- 斜線は定規を使ってまっすぐに引くと印象が良いです。
- 修正液や塗りつぶしは避けましょう。
- 「御中」と「様」を同時に使わないよう注意が必要です。
- 封筒が縦書きの場合は二重線も縦方向に合わせて引き、横書き封筒では横向きに調整すると全体のバランスが整います。
- 斜線を引いた後、上から丁寧に「御中」または「様」を書き足すことで、相手に対する敬意と配慮が伝わります。
- 一筆加えるだけでも印象が変わるため、ビジネス上の細やかな気遣いを意識しましょう。
- 文字が潰れたり、線が交差して読みにくくならないよう、ペンの太さにも注意してください。0.5〜0.7mm程度のペン先が最適です。
書き換えや修正液の使用はNG?
修正液や修正テープで「行」を消すのはマナー違反です。
紙面が汚れるだけでなく、「丁寧さに欠ける」と見られる恐れがあります。
必ず二重線で対応しましょう。
加えて、消しゴムで文字を消す行為も避けましょう。
紙がへこんだり破れたりすると、受け取った相手に「雑な印象」を与えてしまいます。
どうしてもミスをした場合は、新しい封筒に書き直すのがベストです。
手間はかかりますが、それが結果的に信頼を得る最善の方法になります。
ビジネスシーンでの返信用封筒活用法

| シーン | 主な目的 | 敬称の使い方 | 封筒のポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 転職活動 | 応募書類送付・返信書類受取 | 自分宛に「行」記載/相手は「御中」に変更 | 切手を事前貼付・白やクリーム色を使用 | 清潔感と誤送付防止を重視 |
| 就活 | 企業からの書類返信用 | 「行」をつける/相手が「様」に変更 | 住所・郵便番号を正確に記入 | お礼状を添えると好印象 |
| メール併用 | 郵送とメール連絡の併用 | 封筒は従来通り/メールでフォロー | 件名・内容を一致させ混乱防止 | メール+封筒で丁寧な印象 |
転職活動と返信用封筒の使い方
転職活動では、応募書類を送る際に返信用封筒を同封する場合があります。
その場合は「自分の住所+行」を明記し、相手が「御中」に修正しやすいよう配慮します。
さらに、封筒にはあらかじめ切手を貼り、差出人住所や氏名を明瞭に記載しておくことで、企業担当者がスムーズに返信できる環境を整えます。
書類を送る際は、封筒全体の清潔感も重要で、折り目や汚れがないか確認しましょう。
また、複数の企業に応募する場合は、宛名・住所を間違えないようチェックリストを用意しておくと安全です。
返信用封筒の色は白やクリーム色が最適で、過度に派手な色はビジネスシーンでは避けた方が良いでしょう。
細やかな気配りが、相手の印象を左右します。
就活におけるマナーと注意点
就活では、企業からの返信書類を受け取るための封筒に「行」と書くのが基本です。
「御中」を先に書いてしまうと、相手に失礼になるため注意が必要です。
また、封筒には自分の住所を正確に記入することが大切で、特にマンション名や部屋番号の記載漏れが多く見られます。
郵便番号も必ず記入し、郵便局で届かないリスクを防ぎましょう。
宛名を書く際は、なるべく丁寧な文字で書くことを意識し、筆圧が強すぎて裏に透けないようにします。
さらに、返信用封筒を送る際には「お礼状」や「送付状」を添えると、より礼儀正しい印象を与えます。
細かな点ではありますが、これらの積み重ねが採用担当者の印象に大きく影響します。
就活では誠実さと清潔感が評価されるため、封筒一つにもその意識を込めましょう。
メールやはがきとの併用方法
最近では、メールでの連絡と併用するケースもあります。
その場合でも、紙の封筒で返信する際はビジネス書式に則った封筒記載が望ましいです。
メールでの連絡後に返信用封筒を送る場合は、件名や内容を一致させて相手が混乱しないようにすることも大切です。
また、メールと郵送を組み合わせることで、相手に対して迅速かつ丁寧な印象を与えられます。
たとえば、「本日、書類一式を郵送いたしました」といったフォローアップメールを送ることで、ビジネス上の信頼感を強化できます。
さらに、はがきや封書を使う場合には、季節の挨拶や一言メッセージを添えると、形式的なやり取りの中にも温かみを感じさせられます。
こうした工夫が、形式だけでなく人間関係を築く上でもプラスに働くのです。
ケース別文例:ビジネス・就活・公的機関での使い方

【企業宛て・ビジネスシーン】
応募書類送付時の例:
〒100-0001 東京都千代田区○○1-2-3 株式会社○○○○ 御中
返信用封筒(自分宛)
〒123-4567 東京都港区○○○1-1-1 田中○○ 行
→企業側返信時は「行」を二重線で消し「様」へ変更。
取引書類のやり取り例:
株式会社○○○商事 御中 請求書在中
返信用封筒では:
株式会社○○○事 営業部 行
→返信時:「営業部 行」→「営業部 御中」。
問い合わせ書類送付例:
株式会社○○○○○ 御中 (お問い合わせ資料送付の件)
〒123-4567 東京都品川区○○1-1-1 山本○○ 行
【就職活動・転職活動】
エントリーシート送付時の例:
株式会社○○○○○ 御中 採用ご担当者様宛 書類在中
〒100-0001 東京都中央区○○1-2-3 佐藤○○ 行
→担当者が返信時に「行」→「様」に修正。
面接日程の案内返信用封筒(例):
〒101-0021 東京都千代田区○○1-2-3 株式会社○○○○○ 採用担当 行
→返信時:「採用担当 行」→「採用担当 御中」。
内定通知書送付時の返信用封筒(例):
〒150-0002 東京都渋谷区○○4-1-1 高橋○○ 行
→返信時:「行」を消して「様」へ変更。
【学校・教育機関・官公庁】
入試関連書類のやり取り例:
○○大学 入試課 御中
〒999-9999 北海道札幌市○○○1丁目 田中○○ 行
→返信時:「行」を二重線で消し「様」に変更。
資格試験事務局への申請例:
○○協会 試験運営部 御中
〒000-0000 東京都新宿区○○1-1-1 山田○○ 行
→「行」を消し「様」に変更。
官公庁や市役所宛ての例:
○○市役所 総務課 御中
〒123-0001 東京都文京区○○1-1-1 斎藤梨奈 行
→「行」→「様」に修正。
【応用:宛名が複数・部署不明の場合】
部署が分からない場合の例:
株式会社○○○○○ 御中 (採用ご担当者様 宛)
〒123-4567 東京都港区○○3-2-2 佐々木○○ 行
複数部署の可能性がある場合:
株式会社○○○○ 採用担当または人事部御中
〒987-6543 東京都世田谷区○○○2-1-1 森本○○ 行
→返信時、「行」を消して「様」に変更。
【よくあるミスと正しい修正例】
| 間違い例 | 正しい書き方 |
|---|---|
| 株式会社〇〇御中 田中様 | 株式会社〇〇 田中様 |
| ○○会社 行 | ○○会社 御中 |
| 田中太郎 行 様 | 田中太郎 様 |
| 修正液で「行」を消す | 二重線で「行」を消す |
文例の活用ポイント
- 宛名は中央、差出人は左下に整える。
- 敬称は必ず相手の立場に合わせる。
- 「行」→「御中/様」の変換は自然な筆致で。
- 就活・転職・公的書類など、すべての場面で清潔・丁寧・統一感が信頼を生む。
実際のケーススタディとパターン
様々なシーンでの具体例
・企業宛:○○株式会社 御中(返信用封筒:自分の氏名+行)
→企業全体に送る場合。部署や担当者が不明なときに使用します。
・担当者宛:○○株式会社 △△様(返信用封筒:自分の氏名+行)
→担当者名が分かっている場合に使い、より個別対応の印象を与えます。
・学校宛:○○大学 入試課 御中(返信用封筒:自分の氏名+行)
→大学・高校・専門学校など教育機関宛てでは「御中」を用いるのが基本です。
・官公庁宛:○○市役所 総務課 御中(返信用封筒:自分の氏名+行)
→公的機関では必ず部署名+御中を使い、担当者名が分かっても「様」を付けずに統一します。
・団体宛:公益社団法人○○協会 事務局 御中(返信用封筒:自分の氏名+行)
→協会・組合・財団などでも同様に、正式名称を省略せず書くことが信頼感を高めます。
担当者別の書き方の違い
採用担当者や総務部宛ての場合、個人名が分かっているなら「様」、不明な場合は「御中」を使います。
返信用封筒ではあくまで自分が受け取る立場なので「行」を使用します。
また、担当者名が判明している場合は「○○株式会社 採用担当 △△様」と書くことでより丁寧になります。
もし複数名の担当者が関わる場合は「採用ご担当者様」や「採用チーム御中」とするのが無難です。
さらに、社長・部長など役職者への送付時には「様」を付けて「○○株式会社 代表取締役 △△様」と表記します。
肩書や部署を省略せず正式名称で書くことが重要です。
企業名や団体名の記載方法
企業名の後に「御中」を書くときは、団体名全体を含めるのが正しいです。
例:「株式会社ABCマーケティング御中」。
略称や愛称を使うのは避けましょう。
さらに、複数の企業名が併記されている場合やグループ会社の場合には、どの法人に宛てたものかが明確になるように正式名称を省略せず記載します。
英語名を含む会社名(例:ABC Holdings Inc.)の場合でも、「御中」は日本語で書くのが基本です。
また、社名の後にスペースを入れずに「御中」を書くことで、見た目の整ったフォーマルな印象を与えられます。
確認とまとめ

返信用封筒の消し方の要点まとめ
- 「行」を二重線で消して「御中」または「様」を書く。
- 二重線は斜めに、線の間隔を一定にして丁寧に引くと見た目が美しくなります。
- 修正液や消しゴムは使わない。紙面が汚れるだけでなく、マナー面でも印象を損ねます。
- 相手への敬意を示す丁寧な字で書く。
- 字の太さや間隔にも気を配り、封筒全体のバランスを整えると信頼感が増します。
- 「行」を消す位置は宛名の直下や右横に揃え、ずれないよう意識します。
- 消した後の「御中」や「様」はやや小さめに書くことで、全体が上品にまとまります。
注意点とマナー違反の回避法
- 「御中」と「様」の併記はNG。どちらを使うべきか迷ったときは、宛先が個人なら「様」、部署や組織なら「御中」が原則です。
- 線が乱雑にならないようにする。ボールペンや万年筆で定規を使うとまっすぐに仕上がり、信頼感が生まれます。
- 自分の住所や宛名を忘れずに明記。
- 特に返信封筒では郵便番号、住所、氏名の3点が揃っていないと返送が遅れる原因になります。
- 封筒が汚れたり、折れたりしないよう保管方法にも注意。
- インクの色は黒が基本ですが、公式な書類の場合は青黒のインクでも可。いずれも統一感を持たせましょう。
最後に押さえておくべき基本知識
返信用封筒は、小さな紙面でも相手に印象を与える重要なツールです。
正しい「行」の消し方や「御中」の使い分けを理解することで、信頼を損なわず、ビジネスマナーに強い印象を残せます。
また、封筒の扱い方ひとつであなたの印象が左右されます。
清潔な封筒、整った字、丁寧な配置はすべて誠実さを伝える要素です。
細部に気を配ることで、手書きの温かみと配慮が相手に伝わり、結果的により良い関係構築につながります。
ビジネスマナーは形式的なものではなく、相手への思いやりを形にしたものと心得ておきましょう。